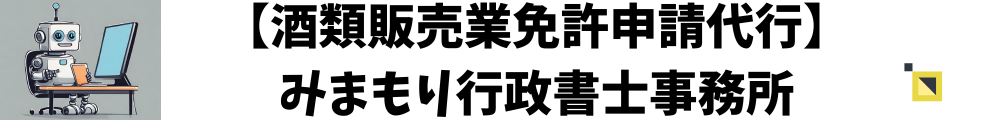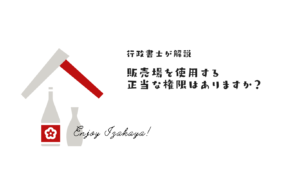複数の販売場がある場合には各々免許が必要です!

複数の販売場がある場合には各々免許が必要です!
Contents
1.酒類販売場が複数ある場合には

①販売場ごとに免許が必要です
ポイント:酒類販売業免許は販売場ごとに必要
よくある誤解として、「一度免許を取得すれば、どこでもお酒を売ってよい」と思われがちですが、これは間違いです。
酒類販売業免許は「場所」に紐づく免許です。
つまり、複数、販売場がある場合にもその場所ごとに免許が必要となります。
例えば、本店で免許を受けていても、支店で酒類販売を行う場合には、その支店の所在地を管轄する税務署長から新たに免許を受けなければなりません。
②販売場とは?

ポイント:そもそも販売場とは
酒税法上、「販売場」とは酒類を実際に販売する場所を指し、一般的な酒屋やワインショップのように消費者が訪れる店舗だけでなく、最終消費者が来店しない事務所も含まれます。
例えば、以下のような事務所形態でも「販売場」として免許が必要になります。
販売場に該当する例
- 事務所に隣接する倉庫から飲食店などに納品する
- 事務所で受注(電話・メール)し、郵送で酒類を発送する
③小売業の場合には、酒類販売管理者についても複数配置が必要になる

酒類小売業免許を取得する場合、販売場ごとに「酒類販売管理者」を1人選任します。
ちなみに、酒類卸売業免許のみ取得の場合は、選任不要です。
つまり、販売場が複数ある場合で尚且つ酒類小売業免許の場合にはそれぞれ、酒類販売管理者の専任が必要です。
ポイント:他の販売場と兼任は不可
他の販売場がある場合に、酒類販売管理者を二つ以上の販売場で兼任することはできません。
なぜなら、酒類販売管理者は、通常、販売場に滞在している人が担当しないといけないからです。
ポイント:酒類販売管理者になれる者は?
酒類販売管理者に選任することができる者は、誰でもいいわけではありません。
下記の要件を満たす者が酒類販売管理者になることができると定められています。
【酒類販売管理者に選任することができる者】
- 未成年者、認知や判断能力に問題がある者、または酒税法の特定規定に該当する者でないこと。
- 酒類小売業者に6か月以上継続して雇用される予定であること(親族や雇用期間の定めがない者も含む)。
- 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者で、3年以上経過していること。
- 過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者
酒類販売管理者は、6か月以上継続して雇用される予定であるという雇用関係があれば、形態に関わらず、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員でも選任することが可能です。
酒類販売管理者について、詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。
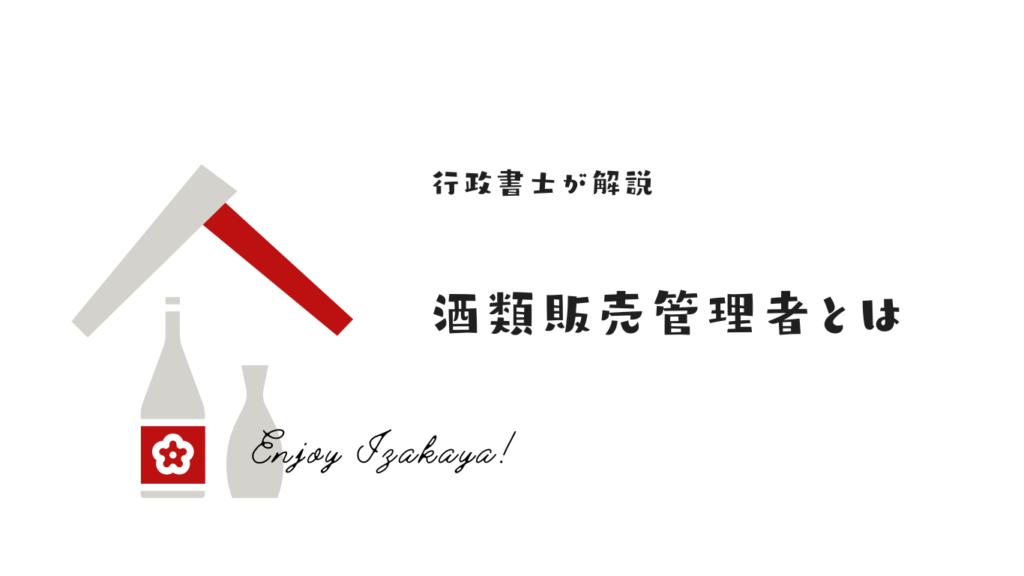
④販売場について、その他の確認しておくべきこと

販売場について、確認すべき事は他にもあります。
具体的には場所的要件と言われるものです。
場所的要件とは?
- 販売場が適当な場所にあるか
- 法律に違反していないか
- 販売場の建物を実際に使用することができるか
など、要件を満たしている必要があります。
具体的には過去の記事で解説していますので、下記からご確認ください。
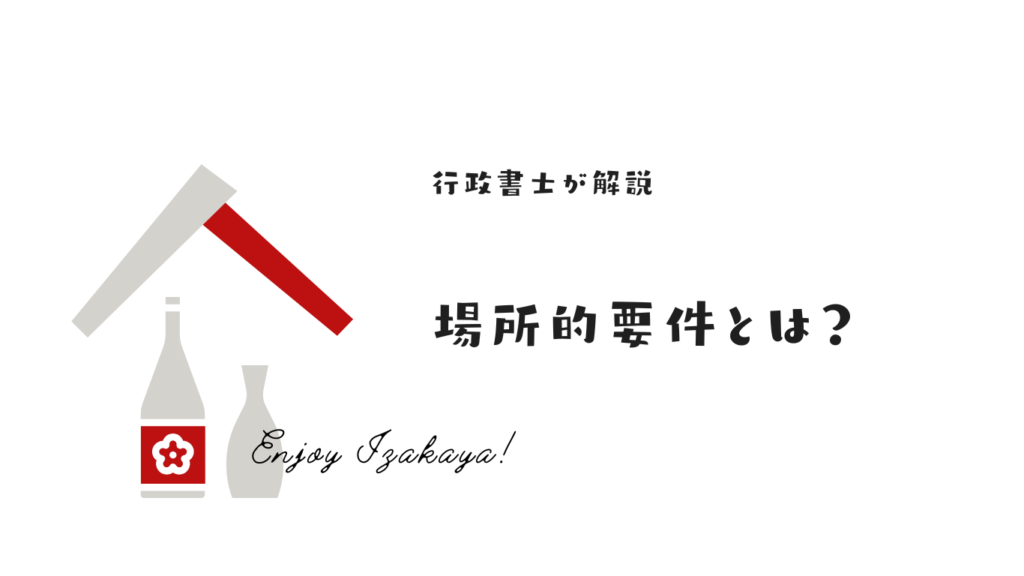
2.まとめ
以上、複数の販売場がある場合には各々免許が必要です!について解説いたしました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい