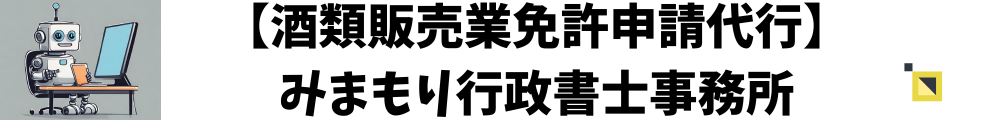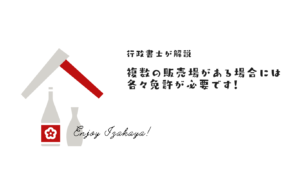【よくあるご質問】酒類販売業免許Q&A

【よくあるご質問】酒類販売業免許Q&A
Contents
1.酒類販売業免許を取得したい!

酒類販売業免許を・・・
- 事業拡大でお酒を販売したい!
- 他社との差別化でお酒を販売したい!
- 副業でお酒を販売したい!
このように、お酒を販売するために、酒類販売業免許を取得したい!という方は多いのではないでしょうか?取得したい理由は人それぞれありますが、酒類販売業免許を取得するために
- これから、何をすれば良いのか?
- 要件は満たせているのか?
- 費用はいくらかかるのか?
など
疑問に思うこと、たくさんあると思います。
ということで、今回は行政書士として酒類販売業免許を専門で申請代行をしている私が依頼者様に頂いたご質問をまとめてみました。
同じ悩みを持たれている方もいらっしゃるかもしれませんので、ぜひ参考にされて下さい。
2.酒類販売業免許申請Q&A

①そもそもお酒を販売するのに免許は必要なんですか?
回答:事業として行うのであれば免許は必要です
仕入れたお酒を販売する場合には「酒類販売業免許」が必要です。
ただし、自宅にあるなどの不用品のお酒を販売する場合には酒類販売業免許は必要ありません。
お酒を仕入れて販売するなど継続的に事業を行う場合には、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
ちなみに、酒類を購入する場合には特別な免許を取得する必要はありません。
これは、一般の消費者が自分で飲むためや贈答用としてお酒を購入する際に、免許が必要ないのと同じ考え方です。
②許可取得までどれくらいかかりますか?
回答:申請先によりますが、申請してから2ヶ月程度かかります
結論から申し上げますと、酒類販売業免許を取得するには2ヶ月は最低かかると言われています。
最低2ヶ月ということは、それ以上かかる可能性が大いにあるということです。
これだけ振れ幅があるのは申請準備期間や、申請先によってかかる時間が大きく変わるからです。
- 申請前にかかる期間(準備期間)
- 必要な証明書の取得や申請書の作成といった準備が必要です。この準備が早く整えば、それだけ許可取得までの期間を短縮できます。
- 申請後にかかる期間(審査期間)
- 申請先での審査時間となります。審査期間は申請先や許可の種類によって異なります。審査期間は短縮することができないため、予め余裕を持ってスケジュールを立てることが重要です。
そのため、準備期間と審査期間を合わせると、2.5ヶ月〜3ヶ月程度はかかると思っておくと良いでしょう。
詳しくは過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください
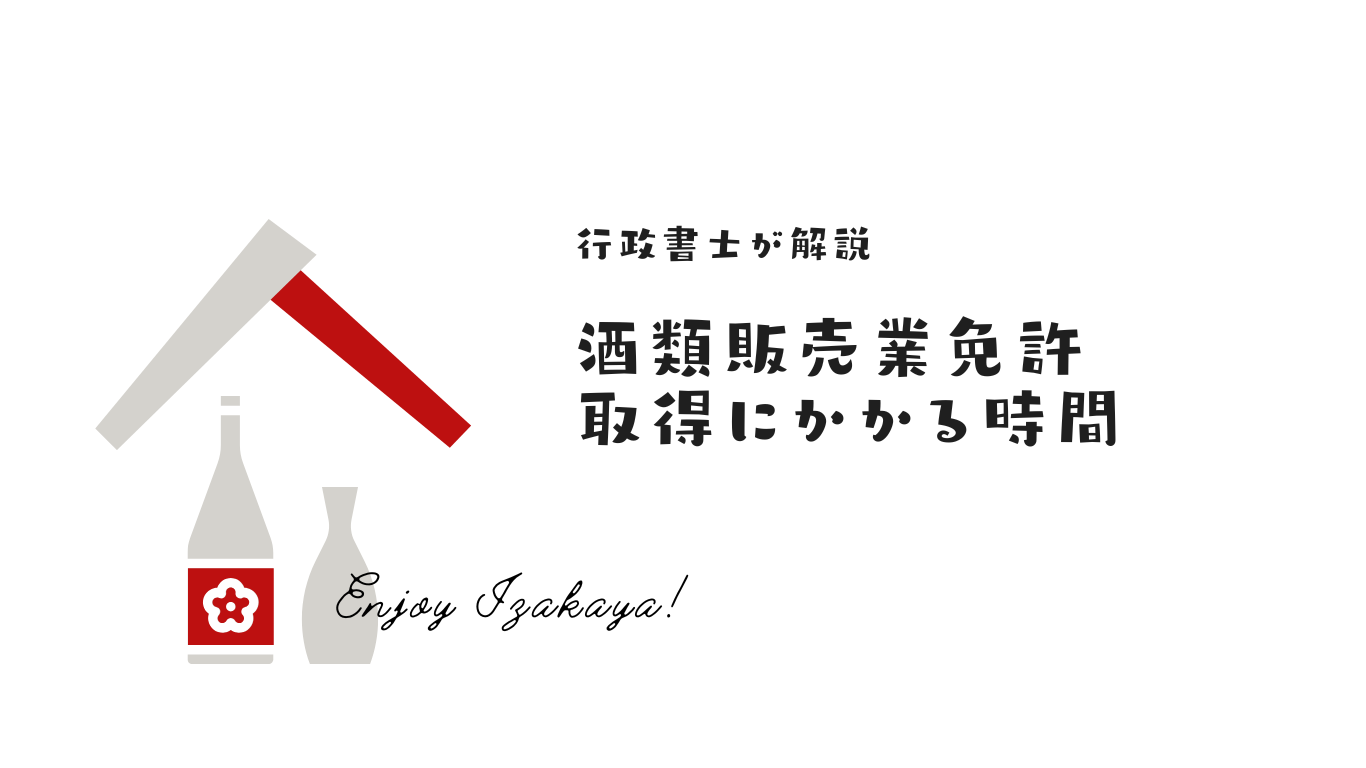
③取得費用はどれくらいかかりますか?
回答:取得する許可の種類によりますので下記をご確認ください
酒類販売業免許を取得する場合には
- 登録免許税
- 行政書士への代行報酬費用
- 証明書などの取得費用
の3つです。
審査手数料と行政書士への代行報酬費用は下記の通りです。
もし、小売と卸売の両方の免許を同時に取得した場合でも、登録免許税は最大90,000円までとされています。
また、後から追加で申請する「条件緩和」も可能です。
新規取得
- 小売のみ
- 30,000円
- 卸売のみ
- 90,000円
- 小売+卸売
- 合計90,000円(最大額)
当事務所にご依頼いただく場合の報酬費用の目安
- 小売業免許(一般小売業・通信販売酒類小売業)
- 143,000円(税込)
- 通信販売とセットの場合は+33,000円(税込)
- 卸売業免許(洋酒・輸出入・店頭販売酒類)
- 143,000円(税込)
取得難易度やご依頼者様の状況によっても違ってきますので、まずは見積を出してもらいましょう。
初回相談は無料です

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい
詳しくは過去の記事でも解説していますので、下記からご覧ください
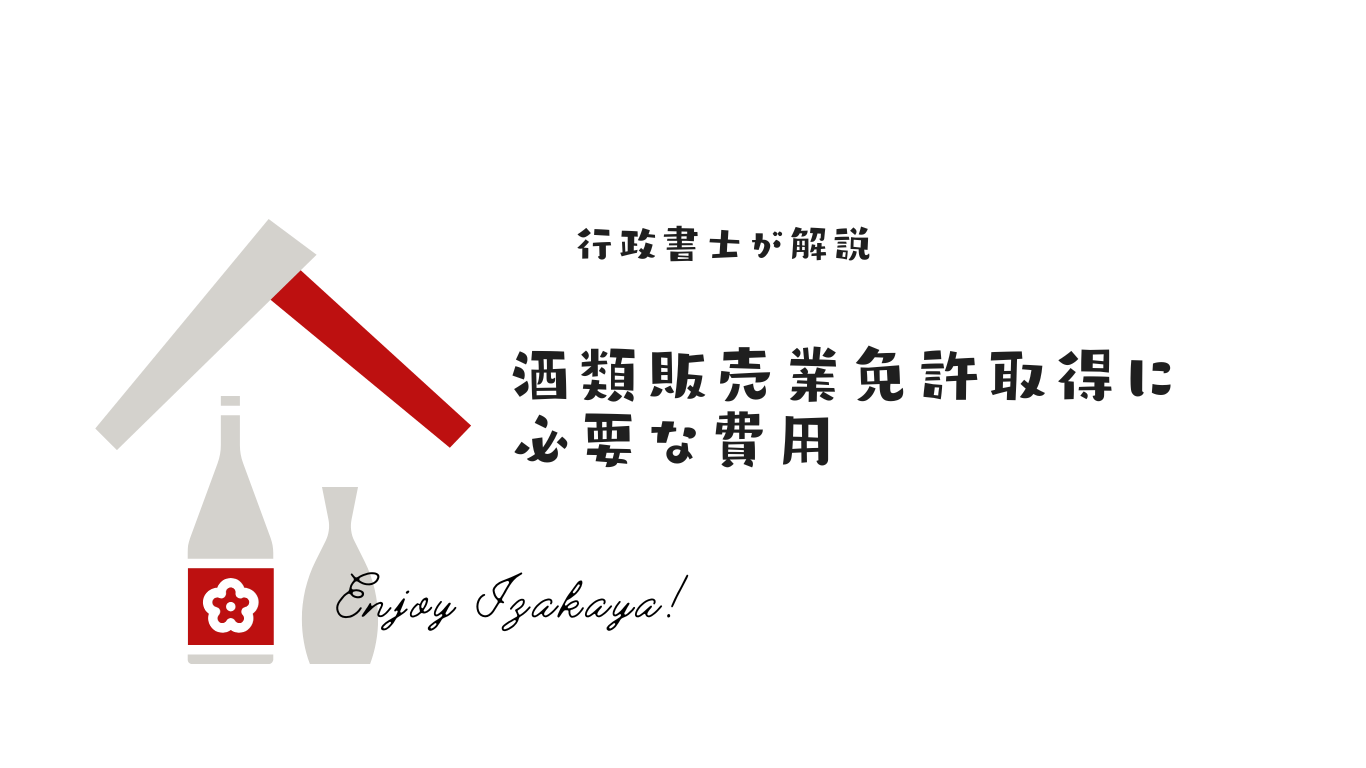
④そもそも自分で申請はできないの?
回答:ご自身で申請することも可能ですが、お勧めしません
酒類販売業免許はご自身で申請することが可能です。
ただし、書類の作成や収集に時間がかかってしまいます。
そもそも、どういった書類を集めればよいか調べるのにも非常に時間を要します。
最悪の場合、許可要件を満たせていないまま申請を進めていて、申請できずに今までやっていたことが、全部無駄になってしまうということもありえます。
それほど、酒類販売業免許の申請は難しいです。
だからこそ、そのようなリスクを回避できたり、時間短縮につながるのは、行政書士に依頼するメリットでしょう。
行政書士に依頼するメリット
- 許可取得できるか事前判断が可能
- 時間の短縮
- 酒類販売業免許に関する情報を聞くことができる
ただし、代行報酬を支払う必要がありますので、コストがかかる点には目を瞑る必要はあります。
⑤自分が要件を満たしているかわからない
回答:まずは電話相談をお勧めします
酒類販売業免許は誰でも取得できるわけではありません。
いくつかの要件をクリアしなければならない他、その要件をクリアしていることを証明する証拠資料を提出しなければなりません
具体的な要件は下記のとおりです
酒類販売業の免許取得要件
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
そのため、まずは許可要件を満たしているか、申請できる状態なのかを相談することをお勧めします。
初回相談は無料です

お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい
⑥2つの販売場がある場合、免許は1つで良いですか?
回答:販売業ごとに免許が必要です。そのため2つ免許が必要です
酒類販売業免許は販売場ごとに免許が必要です。
つまり、別々の場所に販売場がある場合は、免許をそれぞれ取得しなければなりません。
⑦販売管理者は誰でもなれますか?
回答:販売管理者になるための条件はあります
【酒類販売管理者に選任することができる者】
- 未成年者、認知や判断能力に問題がある者、または酒税法の特定規定に該当する者でないこと。
- 酒類小売業者に6か月以上継続して雇用される予定であること(親族や雇用期間の定めがない者も含む)。
- 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者で、3年以上経過していること。
- 過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者
酒類販売管理者は、6か月以上継続して雇用される予定であるという雇用関係があれば、形態に関わらず、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員でも選任することが可能です。
販売管理者については下記のページから解説していますので詳しく知りたい方はご確認ください。
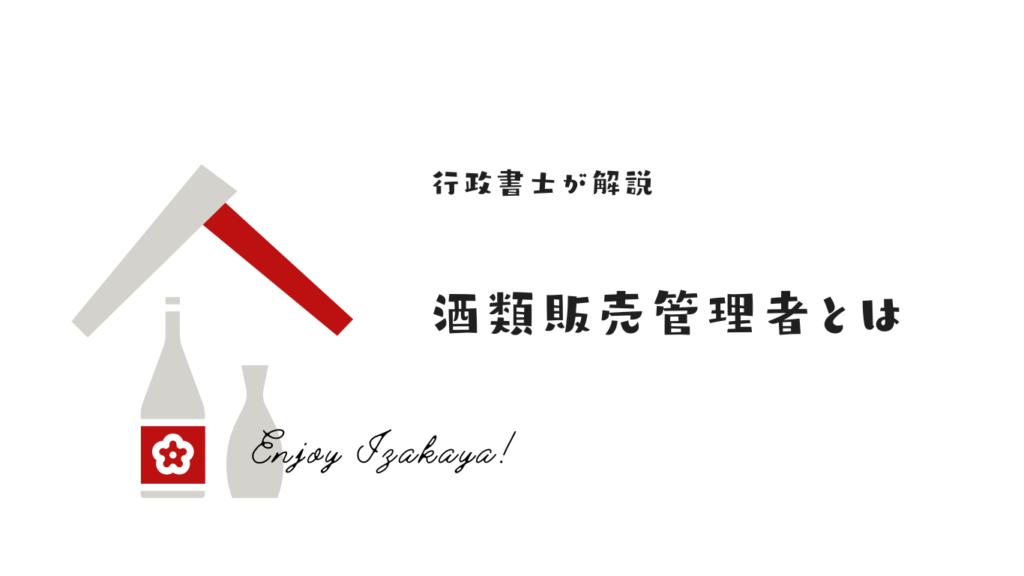
⑧販売管理者は兼任できますか?
回答:原則できません。それぞれ販売場に別の人員配置が必要です
酒類販売小売業免許を取得する場合には、販売管理者の選任が必要です。
この販売管理者は複数の営業所を兼任する事はできません。
酒類販売管理者は下記の者がなることができます。
⑨販売管理者研修はどこで受けられますか?
回答:販売管理者研修は定期的に各地で行われています
販売管理者研修は酒類販売管理者に選任された者が、3年に1度必ず受講しなければならない他、これから酒類販売業免許を取得したい方も受講することになる研修です。
酒類販売管理研修は、財務大臣が指定した団体(例: 一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会、一般社団法人日本ボランタリーチェーン協会、全国小売酒販組合中央会、各地域の小売酒販組合など)が実施しています。
受講の申し込みは各団体のホームページなどで可能です。研修実施団体については、国税庁のホームページ(酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定について)から確認できます。
研修は全国各地で定期的に開催されており、申請販売場とは異なる都道府県での受講も可能です。都合の良い場所や日程を選んで受講しましょう
詳しく知りたい方は下記からご確認いただけます。
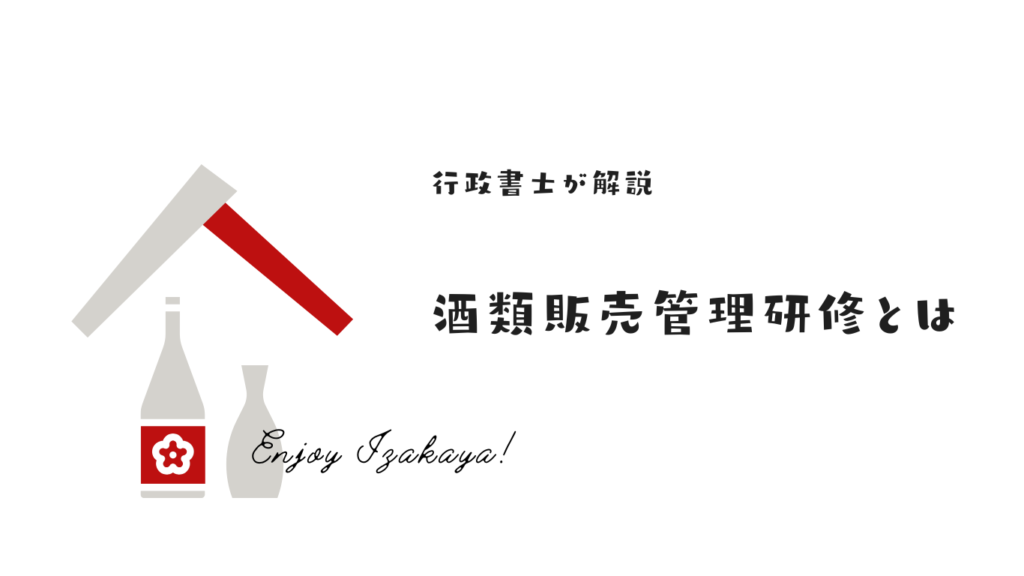
3.まとめ
以上、今回は酒類販売業免許に関してよくある質問をQ&A方式で解説してみました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい