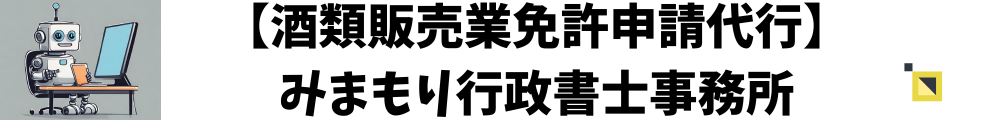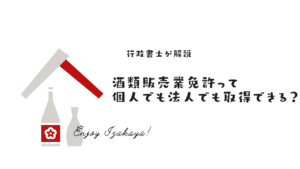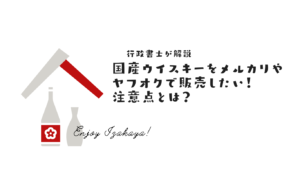飲食店でお酒を提供する場合、酒類販売業免許は必要?

飲食店でお酒を提供する場合、酒類販売業免許は必要?
Contents
1.飲食店では酒類販売業免許が必要なのか?
①原則、酒類販売業免許は必要ありません!

結論から言うと飲食店は原則、酒類販売免許は必要ありません。
飲食店の営業は食品衛生法に基づいて行われるからです。
酒税法にも下記のように記載があります。
(酒類の販売業免許)
e-GOV法令検索より
第九条 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業(以下「販売業」と総称する。)をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)ごとにその販売場の所在地(販売場を設けない場合には、住所地)の所轄税務署長の免許(以下「販売業免許」という。)を受けなければならない。ただし、酒類製造者がその製造免許を受けた製造場においてする酒類(当該製造場について第七条第一項の規定により製造免許を受けた酒類と同一の品目の酒類及び第四十四条第一項の承認を受けた酒類に限る。)の販売業及び酒場、料理店その他酒類をもつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
飲食店で、お客様にお酒をグラスやジョッキで提供する場合、これは「その場で飲用に供する営業」として扱われます。このような営業には、「飲食店営業許可」(食品衛生法に基づく)が必要ですが、「酒類販売業免許」は不要です。
ポイント:開栓してから提供するか、未開栓で販売するか
酒類販売免許が必要なケースはどのように考えれば良いかというと、
「お酒の容器を開栓してから提供するか、開栓せずにそのまま販売するか」の違いがあります。
たとえば、
酒類販売業許可が不要な場合の例
- 瓶ビールを開栓してテーブルに提供
- 焼酎をボトルキープで管理し、店内でのみ提供
といったスタイルであれば、飲食店営業許可のみで問題ありません。
これは、酒税法上「その場で飲むための提供」は販売には該当しないと解釈されているためです。
②例外:お土産用など未開栓のお酒を販売するなら許可が必要

一方、次のようなケースでは酒類販売業免許の取得が必要になります。
飲食店で酒類販売業免許が必要な場合の例
- 瓶ビールやワインを未開栓の状態でお客様に販売し、持ち帰ってもらう(いわゆるお土産販売)
- テイクアウトやデリバリーで料理と一緒にお酒も販売する
- 店舗の一角に陳列棚を設けて、物販として酒類を販売する
これらは、「その場で飲む」ではなく物販としての酒類小売に該当するため、たとえ飲食店が本業であっても税務署からの酒類販売業免許が必要です。
2.飲食店で酒類販売業免許を取得するなら

①飲食店と販売場の区画を分ける
酒税法では、「販売場が酒場や料理店と同一場所でないこと」が原則とされています。
そのため、店舗内で飲食エリアと物販エリアを明確に分けられている必要があります。
申請の際には「酒類販売免許申請書 次葉2 建物等の配置図」を作成する必要がありますが、飲食エリアと物販エリアの区画が分かれているかを審査されます。
②飲食用と物販用のお酒は完全に分けて管理する
飲食用のお酒と物販用のお酒は明確に分けて管理しなければなりません。
具体的には、次のような点で区別が必要です。
- 仕入先を分ける
- 飲食用は小売業者、物販用は卸売業者から仕入れなければならない
- 在庫の保管場所を分ける
- 飲食用のお酒と物販用のお酒を同じ冷蔵庫等に保管することは不可
- 帳簿やレジを分けて管理する
- POSレジなどで部門ごとに売上管理を分けられる体制が必要
3.まとめ
以上、飲食店でお酒を提供する場合、酒類販売業免許は必要?を解説しました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい