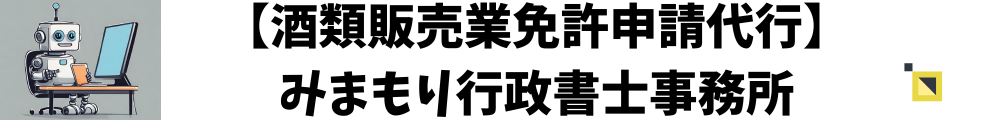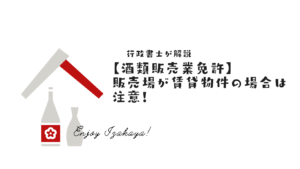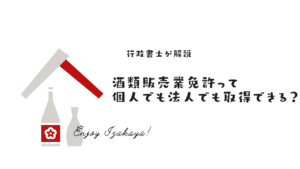お酒の免許取得に経験が必要なのか?

お酒の免許取得に経験が必要なのか?
Contents
1.経営基礎要件をクリアする必要がある
①経営基礎要件とは

3 酒税法 10 条 10 号関係の要件(経営基礎要件)
一般種類小売業免許申請の手引より引用
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと
経営起訴要件では、免許の申請者が経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないことが、要件として求められています。詳細は別ページで解説していますので、今回は省略しますが、他にも満たす必要のある経営基礎要件があるのはご存知でしょうか?
②最低限の経営経験は必要
チ 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること合に該当しないこと
リ 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められること
一般種類小売業免許申請の手引より引用
ポイント:酒類販売を適正に経営できるだけの知識や能力が必要
上記のように申請者(法人の場合はその役員)が酒類販売事業を適正に経営できるだけの知識や能力、経験などが必要となります。
今回はこの経営できる知識や能力経験などについて詳しく解説していきます。
2.酒類販売業免許の審査で見られる「経験」とは?

①他業種での経営経験+酒類販売管理者研修の受講でOKな業種
申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
1 免許を受けている酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に引き続き3年以上直接従事した者、調味食品等の販売業を3年以上継続して経営している者又はこれらの業務に従事した期間が相互に通算して3年以上である者。
なお、これらの従事経験や経営経験がない場合には、その他の業での経営経験に加え「酒類販売管理研修(17 頁参照)」の受講の有無等から、①酒類の特性に応じた商品管理上の知識及び経験、②酒税法上の記帳義務を含む各種義務を適正に履行する知識及び能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力が備わっているかどうかを実質的に審査することになります。2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類の製造業若しくは販売業の経営者として直接業務に従事した者等で酒類に関する事業及び酒類業界の実情に十分精通していると認められる者。
一般種類小売業免許申請の手引より引用
必要な経験まとめ
- 酒類の製造・販売業務に3年以上従事したことがある
- 味噌・醤油など発酵食品や調味料などの販売業を3年以上営んでいる
- 他業種で経営経験があり、さらに「酒類販売管理研修」を受講している
①−1少なくとも3年以上の経営経験が最低条件ラインの業種
他業種での経営経験3年+酒類販売管理者研修の受講でOKな業種
- 一般酒類小売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
- 店頭販売卸売業免許
- 協同組合員間酒類卸売業免許
必要な経験まとめ
- 酒類の製造・販売業務に3年以上従事したことがある
- 味噌・醤油など発酵食品や調味料などの販売業を3年以上営んでいる
- 他業種で経営経験があり、さらに「酒類販売管理研修」を受講している
酒類の販売や製造に直接関わった経験がない場合でも、他業種での経営経験に加えて「酒類販売管理研修」を受講することで、必要な知識を補うことが可能です。
経営経験については、代表取締役に限らず、取締役としての経験も認められます。また、個人事業主として事業を行っていた経歴も評価の対象になります。
経営の経験年数としては、必ず3年必要であると断言はできませんが、少なくともおおむね1年から3年程度あることが望ましいとされています。
ポイント:3年分の確定申告書の提出が必要
経営経験が3年以上ある証明に必要な書類である3年分の確定申告書の提出が必要になります。
法人の役員経験がある場合には商業登記の謄本で経験年数を確認される場合もありますが、どちらにせよ、確定申告書の提出は必要となりますので、用意しておくようにしましょう。
①−2経営経験が3年なくてもOKな業種
他業種での経営経験+酒類販売管理者研修の受講でOKな業種
- 輸入酒類卸売業免許
- 輸出酒類卸売業免許
必要な経験まとめ
- 酒類の製造・販売を経験した、または経営していた
- 他業種での経営実績+研修受講
- 貿易実務の経験があり、さらに酒類販売管理研修を受けている
ポイント:経営経験が3年なくてもOK
輸入・輸出酒類卸売業免許に関しては、明確な年数が示されていないため、経営経験が3年なくても、酒類販売管理研修を受講することで取得できます。
②酒類の製造業若しくは販売業の経験が必ず必要な業種

申請者(申請者が法人の場合はその役員)及び申請販売場の支配人がおおむね次に掲げる経歴を有する者で、酒類に関する知識及び記帳能力等、酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有し、独立して営業ができるものと認められる場合は、原則として、この要件を満たすものとして取り扱うこととしています。
【全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許に係る申請等の場合】
酒類卸売免許申請の手引より引用
1 酒類の製造業若しくは販売業(薬用酒だけの販売業を除く。)の業務に直接従事した期間
が引き続き 10 年(これらの事業の経営者として直接業務に従事した者にあっては5年)以
上である者、調味食品等の卸売業を 10 年以上継続して経営している者又はこれらの業務に
従事した期間が相互に通算して 10 年以上である者。
2 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者又は酒類に関する事業及び酒類
業界の実情に十分精通していると認められる者。
3 申請等販売場が沖縄県に所在する場合の申請者等の経歴については、1に定める期間が 10
年とあるのを3年と読み替えます。
ポイント:ビール卸売業免許・全酒類卸売業免許は要件が厳しい
ビール卸売業・全酒類卸売業免許は最も経験要件が厳しく、下記のような条件が設定されています。
ビール卸売業免許や全酒類卸売業免許は、酒類業界に精通した人が取得できる免許と考えておくとよいでしょう。
ビール卸売業・全酒類卸売業免許
- 酒類製造・販売業に10年以上従事(沖縄県内の販売場は3年以上)
- 上記を5年以上経営している(沖縄県内は3年以上)
- 調味料などの卸売業を10年以上継続して経営している
- 酒類関連団体で長期間勤務した実績がある
ポイント:その他にも厳しい要件のクリアが必要
全酒類卸売業・ビール卸売業免許の取得難易度の高い理由
- 免許可能件数が限られている
- 申請者は販売場の所在地が特定の都道府県にあることが条件で、各都道府県ごとに年度ごとの免許可能件数が設定されており、ほとんどの県が1件、多くても3~6件しかありません。
- 抽選制度
- 毎年9月1日から30日までの1か月間だけに抽選申し込みが行われ、希望者が多い場合は抽選で審査順位が決定されます。
- 厳しい申請条件
- 10年以上の酒類業界の従事経験(経営経験の場合は5年以上)が必要であり、さらに年間の予定卸売数量が100kl(10万リットル)以上であることが求められます。
3.まとめ
以上、酒類販売業免許の販売場を賃貸物件にする場合の注意点を解説いたしました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい