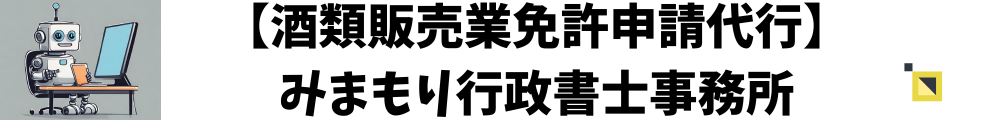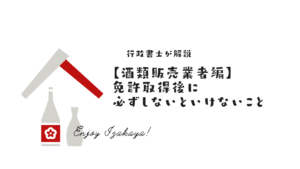酒類販売業免許を取得するならまずはこれをしよう!

酒類販売業免許を取得するならまずはこれをしよう!
Contents
1.販売するお酒の種類や販売する相手を考えよう

酒類を販売する場合、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
①販売したいお酒がなんなのか?
ポイント:販売したいお酒によって販売方法が変わる
何のお酒を販売したいのかのかをまずは考えましょう。
酒類販売業免許は、お酒の種類ごとに区分されており、販売できる酒類の種類を細かく指定する必要があります。
お酒の種類によっては「小売りしかできない」とか、「卸売りしかできない」ということがあります。
| 免許の種類 | 種別 | 取扱可能な酒類の例 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 小売業 | 全酒類 | 店舗での対面販売が主。 ほぼ全種の販売が可能。 条件付きで通販も可能 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 小売業 | 輸入酒類 国産酒類(中小酒造業者製造分に限定) | 通販専用。 国産酒類は課税出荷量3,000kl未満の酒造業者製造品に限る。 |
| 全酒類卸売業免許 | 卸売業 | 全酒類 | 業者向けに、すべての種類の酒類を販売可能。取得難易度高。 |
| ビール卸売業免許 | 卸売業 | ビールのみ | ビール専門の卸売免許。取得難易度高 |
| 洋酒卸売業免許 | 卸売業 | 洋酒:ワイン(果実酒)、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、リキュール、スピリッツ等 | 洋酒であれば国産でも外国産でも可能 |
| 輸入酒類卸売業免許 | 卸売業 | 輸入された酒類全般 | 日本国外で製造された酒類に限定。 |
| 輸出酒類卸売業免許 | 卸売業 | 輸出するものであれば制限なし | 日本国外との取引前提。 海外ECサイトで販売する場合に必要 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | 卸売業 | 自社ブランドの酒類のみ | 自社で商標登録した酒類に限り販売可能。 |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 卸売業 | 原則すべて(※販売先の限定あり) | 会員登録された卸売業者のみで店頭販売に限る |
酒類販売業免許の種類については下記から
②免許の種類によって取得難易度が変わる

酒類販売業免許を取得する場合、下記の許可要件をクリアしなければなりません。
酒類販売業の免許取得要件
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 需給調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。
ポイント:経営基礎要件や需要調整要件は特に重要
酒類販売業の経験がどれくらいの年数あるか、年間どれくらいの販売数量があるかなどによって、取得できる免許は変わります。
例えば、全種類卸売業免許やビール卸売業免許に関しては、かなり厳しい条件が課されています。
全酒類卸売業免許やビール卸売業免許の取得難易度が高い理由
- 免許可能件数が限られている
- 申請者は販売場の所在地が特定の都道府県にあることが条件で、各都道府県ごとに年度ごとの免許可能件数が設定されており、ほとんどの県が1件、多くても3~6件しかありません。
- 抽選制度
- 毎年9月1日から30日までの1か月間だけに抽選申し込みが行われ、希望者が多い場合は抽選で審査順位が決定されます。
- 厳しい申請条件
- 10年以上の酒類業界の従事経験(経営経験の場合は5年以上)が必要であり、さらに年間の予定卸売数量が100kl(10万リットル)以上であることが求められます。
ポイント:最初に取得するなら
最初に取得するなら、
- 一般酒類小売業免許
- 通信販売酒類小売業免許
- 洋酒卸売業免許
あたりが取得しやすいです。
経営基礎要件として、概ね3年間以上、酒類販売を行った経験があるか求められます。
ただ、確かに3年分の確定申告書を提出できるかなどの経営経験を証明できることは最低限必要ですが、酒類販売自体の経験がなくても、酒類販売管理者研修を受講すれば要件クリアが可能です。
とはいえ、他にもクリアしないといけない要件があるのでその点は下記から確認しておきましょう。
許可要件の詳細は下記から
2.取得したい免許が決まったらとりあえずやっておくべき事

取得したい免許が決まったら、要件を満たすため、必要な書類などを用意することになります。
免許の種別ごとに用意する書類は当然変わってくるのですが、大まかにいえば、小売業免許なのか卸売業免許なのかによって、やるべきことが変わります。
とりあえず最初にやっておくべきことについて、解説します。
①酒類小売業免許の場合には
ポイント:酒類販売管理者を選任するための準備
酒類小売業者は必ず、酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理者は、簡単にいえば店長のような人を指すのですが、選任することができる者は、誰でもいいわけではありません。
下記の要件を満たす者が酒類販売管理者になることができると定められています。
酒類販売管理者に選任することができる者
- 未成年者、認知や判断能力に問題がある者、または酒税法の特定規定に該当する者でないこと。
- 酒類小売業者に6か月以上継続して雇用される予定であること(親族や雇用期間の定めがない者も含む)。
- 他の販売場で酒類販売管理者に選任されていない者で、3年以上経過していること。
- 過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた者
ポイント:雇用するか研修を受けるか
酒類販売管理者を専任するなら、条件に合う人を雇用するか、ご自身で研修を受けて自分がなるかのどちらかです。
兼任することはできませんので、別の販売場で酒類販売管理者になっている場合は、注意しましょう!
詳しく知りたい方は過去の記事で解説しているので下記からご確認ください。
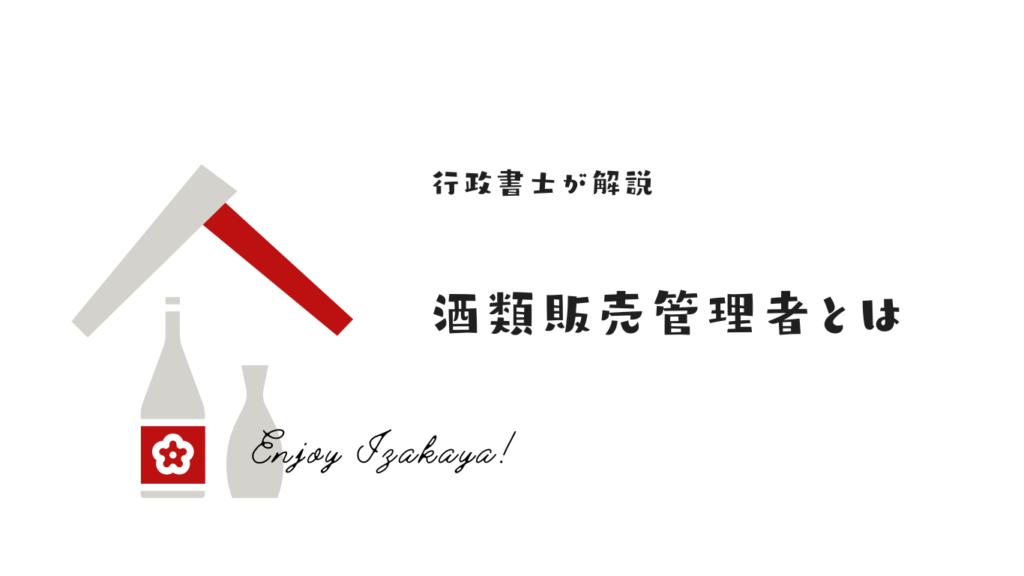
②酒類卸売業免許の場合には

ポイント:原則、仕入れ先と卸売先の両方の取引承諾書が必要
取引承諾書は、仕入先と卸売先(販売先)のそれぞれから1社以上取得する必要があります。
- 仕入先
- 蔵元やブルワリー、ワイナリーなどの製造業者や、酒問屋、インポーターなどの卸業者が含まれます。
- 卸売先
- 酒屋やスーパー、コンビニ、デパートなどのお酒の販売業者が該当します。
酒類販売事業者間でのみ取引ができる「卸売業免許」では、一般消費者や飲食店は販売先として認められませんのでご注意ください。
ポイント:仕入れ先が不特定の相手の場合には
仕入れ先が一般消費者の場合など不特定の相手であれば、仕入れに関しての取引承諾書は不要です。
仕入れ先が不特定の相手の例
- 遺産整理業を行なっており、不用品であるお酒を客から買い取っている
- 古物商を行なっており、持ち込まれたお酒を買い取っている
- インターネット上でお酒を買い取っている
ポイント:全ての取引先から取得する必要はない
取引承諾書は、仕入先・卸売先それぞれから1部ずつ取得すれば十分であり、すべての取引相手から取得する必要はありません。
取引承諾書には、以下の項目を記載する必要があります。
取引承諾書の記載項目
- 宛名
- 承諾内容
- 「酒類卸売業免許を取得した際には、酒類の取引を承諾する旨」
- 日付
- 住所
- 記名・押印
- 海外の場合はサイン
3.まとめ
以上、酒類販売業免許を取得するならまずはやっておくべきを解説いたしました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい