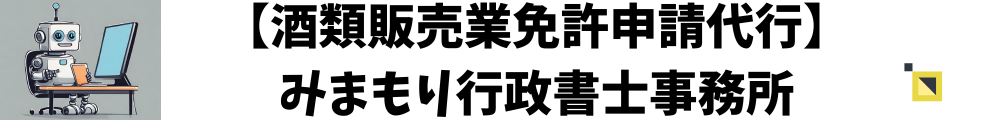事業拡大におすすめ!酒類販売業と相性の良い事業とは?

事業拡大におすすめ!酒類販売業と相性の良い事業とは?
Contents
1.事業拡大に酒類販売業?
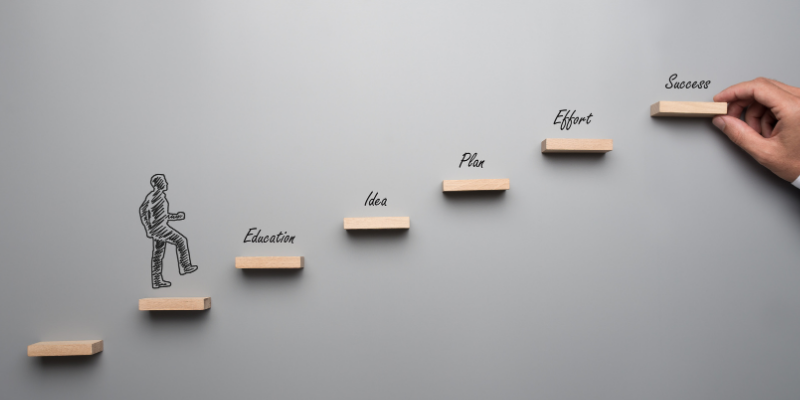
事業の成長や安定した収益基盤の確保のために、新たな柱を検討している事業者にとって、「酒類販売業の導入」は有力な選択肢の一つといえます。
酒類は嗜好品として幅広い層に需要があり、一定の価格帯と利益率を保ちやすい商材です。その中でも、サントリー「山崎」や「白州」、ニッカの「竹鶴」など、国産ウイスキーの品質が国内外で高く評価され、プレミア価格がつくほど需要が急増していることをお聞きになられている方は多いのではないでしょうか?
しかも、仕入れから販売までのスキームが明確で、免許さえ取得すれば既存の事業と掛け合わせて展開しやすいという特長があります。特に、店舗型ビジネスやオンライン販売、飲食業などの事業者であれば、すでに顧客基盤や販売インフラを有しているため、比較的少ない負担で事業の幅を広げることが可能です。
お酒の販売は単独で始めるよりも、既存の事業と組み合わせて展開することで、より大きなシナジーを生み出すことができます。
今回の記事では、事業拡大におすすめの酒類販売業と相性の良い事業について解説いたします。
2.酒類販売業と相性の良い事業
①リサイクルショップ(古物商) × 酒類販売業免許

ポイント:中古酒類のニーズ拡大に対応できる
近年、未開封の国産ウイスキーや海外製ワイン・ブランデーなどが中古市場で高値で取引されることが増えています。特にサントリーの「山崎」「響」、ニッカの「竹鶴」などは人気が高く、オークションやフリマサイトでも頻繁に見かけます。
リサイクルショップや買取業では、これらの酒類を取り扱うことで新たな収益源を確保できます。
ちなみに古物商を営む場合には「古物商許可」を取得する必要があります。
ポイント:お酒は古物の分類に該当しない
原則としてお酒の買取や販売には古物商許可は不要です。
古物商許可が必要かどうかは、先述の通り、取り扱う商品が「古物」に該当するかで判断しますが、「古物」は「古物営業法施行規則」により13品目に分類されており、お酒は法律上「古物」の分類に含まれません。
そのため、中古のお酒だとしても古物商許可は取得は不要です。
ただし、お酒を販売する以上、酒類販売業免許が必要となります。
詳細を知りたい方は下記のページでご確認いただけます。
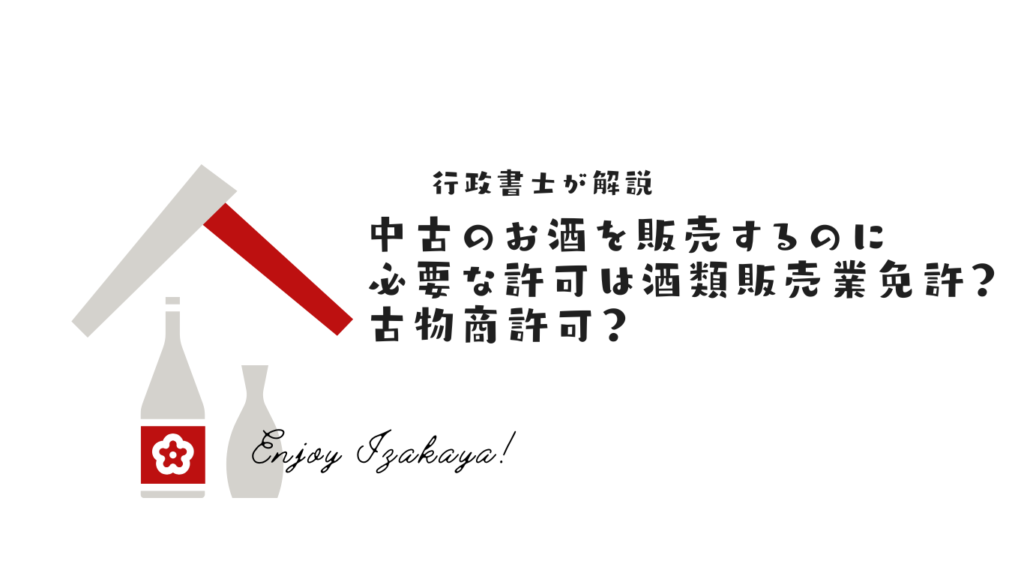
ポイント:店頭販売にも対応しやすい
すでに店舗を運営しているリサイクルショップであれば、「一般酒類小売業免許」を取得することで、買取と同時にお酒の店頭販売が可能になります。
一般酒類小売業免許を取得することで、すべての種類のお酒が販売可能となります。
また、インターネット販売を検討する場合は、「通信販売酒類小売業免許」や条件付きでの「一般酒類小売業免許」の活用も視野に入ります。
②遺品整理業(古物商) × 酒類販売業免許

ポイント:遺品として見つかったお酒を再販できる
遺品整理の現場では、未開封のお酒が見つかるケースが少なくありません。
特に年代物のウイスキーや焼酎などは市場価値が高く、丁寧に取り扱えば高値での売却も可能です。
このような場面で、酒類販売業免許を保有していれば、遺品として見つかったお酒を適切に買い取り、店頭やオンラインで販売することができます。
通常、遺品整理業者はリサイクル品の取り扱いや古物商許可を持っている場合が多く、酒類の扱いも自然な流れで組み込むことができます。ただし、酒類は古物に該当しないため、販売には別途酒類販売業免許が必要です。
古物商許可と酒類販売業免許を取得しておくことで、遺産整理や生前整理の現場で見つかった酒類を適法に買取・販売できる体制が整い、ワンストップでサービス提供が可能になります。
「不要品の整理」と「価値ある品の再流通」を同時に実現できる点において、遺産整理業との親和性は非常に高いといえるでしょう。
当事務所では古物商許可取得も代行することが可能です。
気になった方は下記からご確認ください。
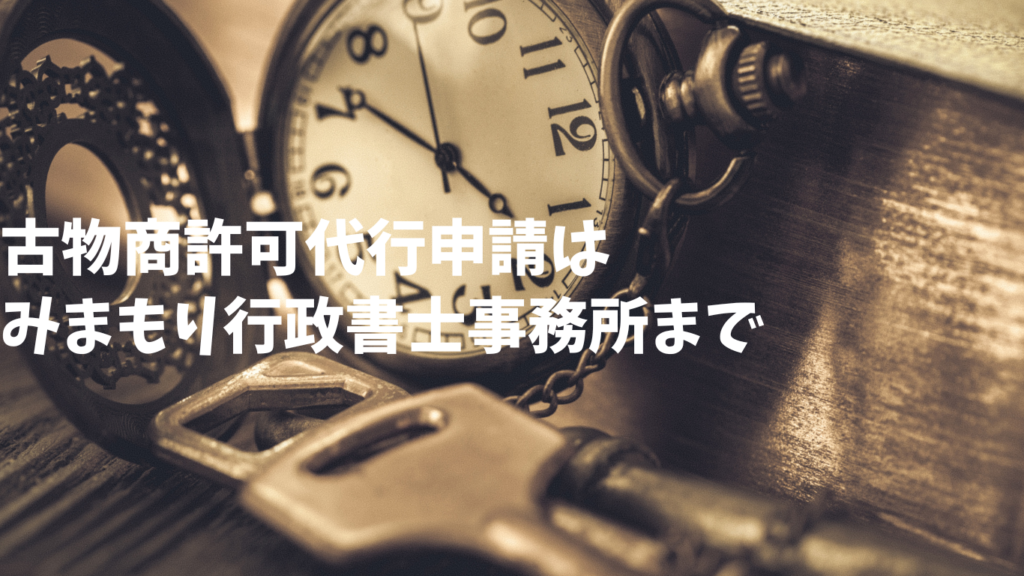
③ECサイト運営 × 酒類販売業免許

ポイント:小規模事業者でもスタートしやすい
オンラインストアやフリマアプリを活用したビジネスは、初期コストを抑えて始められる点が大きな魅力です。インターネット上で酒類を販売する場合に活用できる免許は「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」です。
ただし、通信販売酒類小売業免許では、原則として大手メーカーの国産ウイスキーや日本酒などは販売できません。中小メーカーが製造した酒類で「課税移出数量証明書」を取得したものであれば、販売が可能です。
本格的に国産ウイスキーも扱いたい場合は、「一般酒類小売業免許」を取得し、販売対象を同一都道府県内に限定することで対応する方法もあります。
「輸出酒類販売業免許」を取得すれば、海外のECサイトで国産ウイスキーに限らず、全種類の国産酒を販売することができます。
このように、ECサイトで物販をしている場合には、酒類を販売できるようになることで、他社との差別化もすることができます。
国産ウイスキーをインターネット上で販売したい方は過去の記事で詳しく解説していますので、下記からご確認ください。
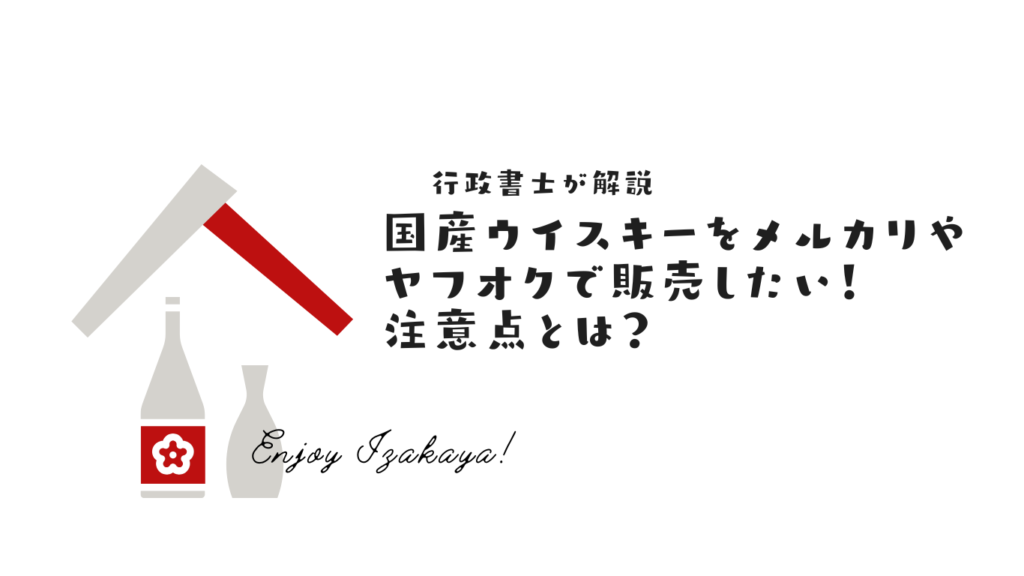
④飲食店(バー・レストラン・居酒屋) × 酒類販売業免許

飲食店で、お客様にお酒をグラスやジョッキで提供する場合、これは「その場で飲用に供する営業」として扱われます。このような営業には、「飲食店営業許可」(食品衛生法に基づく)が必要ですが、「酒類販売業免許」は不要です。
ただし、来店客に未開栓のボトルを販売するには酒類販売業免許が別途必要です。
ポイント:お土産用としてボトル販売
飲食店では日常的にお酒を提供しているため、店頭販売との親和性が非常に高い業種です。飲食店で使用している銘柄を「気に入ったので家でも飲みたい」といったニーズは少なくありません。これを活かして、店頭でボトル販売を行うことで追加の売上が見込めます。
必要になるのは「一般酒類小売業免許」で、販売場(飲食店)で対面販売を行うことが前提です。物販スペースを確保し、在庫管理ができる体制を整えれば、すでに顧客との接点があるため導入のハードルは低く、効果も期待しやすいでしょう。
また、記念日や贈答用のギフト販売を組み合わせれば、飲食だけでない多角的な収益構造をつくることが可能になります。
3.まとめ
以上、事業拡大におすすめ!酒類販売業と相性の良い事業とは?を解説いたしました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい