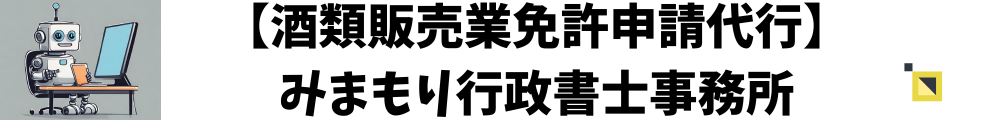中古のお酒を販売するのに必要な許可は酒類販売業免許?古物商許可?

中古のお酒を販売するのに必要な許可は酒類販売業免許?古物商許可?
1.お酒の買取や取引に必要な許可とは?古物商?
①中古の酒の取引が増えてきている

ポイント:中古のお酒が持ち込まれたらどうする?
近年、リサイクルショップや買取専門店で「中古のお酒」を取り扱うケースが増えています。
また、インターネットやオークションサイトでの取引も活発になり、希少価値の高いウイスキーやワインが高値で取引される場面もテレビなどでよく見られるようになりました。
中古品のお酒・・・?
中古品を継続的に取り扱う場合、古物商許可が必要と聞いたことあるのでしょうか?
ただ、中古品とはいえ、お酒。
この場合必要な免許(許可)って
酒類販売業免許? それとも 古物商許可?
どちらだと思いますか?
2.そもそも古物商許可とは?
①古物とは

第二条 定義
古物営業法第2条第1項(e-GOV法令検索より引用)
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
古物とは、「一度使用された中古品」を指すものですが、それだけに限りません。一度も使用されていないが購入や譲り受けた品物、あるいは、それらに修理などの手入れを施したものも古物に含まれます。
②古物商とは
古物商に該当するパターン
- 買い取った中古品を転売する
- 買い取った中古品を修繕するなどして販売する
- 買い取った中古品をレンタルする
- 買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
- 自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
- 国内で買い取った中古品を海外で販売する
- 古物を別のものに交換する
上記のような古物を継続的に売買したり取引することを古物商と言います。
③古物商許可とは

ポイント:古物商取引をするなら古物商許可が必要
中古品(古物)の売買、交換、レンタルなどを業として行う場合は、必ず古物商許可を取得しなければなりません。
許可を得ずに営業すると法律により処罰されます。
これは、車を運転するのに運転免許が必要であるのと同じ考え方です。
罰則
- 懲役3年以下または100万円以下の罰金もしくは併科
- 無許可営業
- 名義貸し
- 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
- 公安委員会の営業の停止命令などに違反した者
また、店舗だけでなく、ホームページやネットオークションで継続的に中古品を取り扱う場合も、古物商許可が必要です。
「業として行う」とは、中古品の売買などを利益を得る目的で継続的に繰り返す行為を指します。
中古品として一般的にイメージされるのは、古本、古着、中古家電、中古家具、中古車、骨董品、中古CD・DVDなどが挙げられます。
これらの中古品の売買等を業として行う際には、古物商許可を取得することで適法に営業することができます。
3.結局、どちらの免許(許可)が必要なのか?
①必要なのは酒類販売業免許

ポイント:お酒は古物の分類に該当しない
原則としてお酒の買取や販売には古物商許可は不要です。
古物商許可が必要かどうかは、先述の通り、取り扱う商品が「古物」に該当するかで判断しますが、「古物」は「古物営業法施行規則」により13品目に分類されており、お酒は法律上「古物」の分類に含まれません。
そのため、お酒の取引を行う場合は古物商許可は必要ありません。
古物の種類
| 01. 美術品類 | 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など |
| 02. 衣類 | 和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など |
| 03. 時計・宝飾品類 | 時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など |
| 04. 自動車 | 自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど |
| 05. 自動二輪車及び原動付自転車 | バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど |
| 06. 自転車類 | 自転車本体、かご、サドル、サイドミラーなど |
| 07. 写真機類 | カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など |
| 08. 事務機器 | パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど |
| 09. 機械工具類 | スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む) |
| 10. 道具類 | 家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど |
| 11. 皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など |
| 12. 書籍 | 文庫本、雑誌など |
| 13. 金券類 | 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など |
ポイント:容器やボトルそのものに価値がある場合は例外の可能性も
ただし、例外的にお酒の容器やボトルそのものに価値がある場合(例:デザイン性の高いボトルやコレクターアイテムの瓶)は、「容器」を古物として扱う可能性があります。
この場合は古物商許可が必要になるケースもあるため、判断に迷った際は警察署の生活安全課に相談すると安心です。
ポイント:お酒の買取は免許不要
酒税法では「販売業免許」についての規定はありますが、「購入するための免許」という規定はありません。
つまり、酒類を購入する場合には特別な免許を取得する必要はありません。
これは、一般の消費者が自分で飲むためや贈答用としてお酒を購入する際に、免許が必要ないのと同じ考え方です。
②酒類販売業免許と相性の良い古物商許可
酒類販売業免許と古物商許可は相性が良いです。
酒類販売業免許と古物商許可を活用したビジネスモデルを2つご紹介しましょう。
②ー1 店頭買取で相性が良い

古物商許可を取得すると、中古品の買取・販売を行うことが可能になります。
ブランド品や家電製品などと同様に、酒類も状態や銘柄によっては高値で取引されるため、店舗における買取ニーズは年々増えています。
一方、酒類を販売するには、たとえ中古品であっても「酒類販売業免許」が必要です。酒類は古物には該当しないため、古物商許可だけでは販売できません。
そこで、両方の許認可を取得しておくことで、「店頭でお酒を買い取り → そのまま販売」といった一連の流れを一つの店舗で完結させることが可能になります。
販売相手によって、取得する酒類販売業免許の種類は変わってきますが、
- 店頭販売するなら
- 「一般酒類販売小売業免許」
- 通信販売するなら、
- 「通信販売酒類小売業免許」※輸入酒類、一部の国産酒類に限る
- 同業者(酒類販売業者)に販売するなら
- 各種「酒類卸売業免許」
など、用途は様々です。実店舗があるのであれば、既存の営業所を活かして新たな収益源を確保することが可能になるでしょう。
②ー2 遺品整理業で相性が良い
相続が発生すると問題になるのが、遺品整理です。
遺品整理は一見シンプルな作業に思えますが、遺族が実家から離れた遠方に住んでいる場合や、遺された遺族自身が高齢であるケースが増えており、遺品整理が次第に困難になってきているのが現状です。
そういった時に利用されるのが、遺品整理業者です。
単に家財を撤去・処分する残置物撤去業者とは異なり、遺品の整理や仕分けを行う点が特徴です。
遺品整理の場面では、故人の自宅から高級酒や骨董品、時計、ブランド品など、さまざまな資産価値のある物品が見つかることがあります。こうした品を処分・売却するニーズに対応できるのが「古物商許可」です。
ただし、未開封のウイスキーやワインなどが遺品で出てきた場合に古物商許可だけでは酒類の売買ができないため、せっかく買取をしても再販ができず、機会損失になるケースもあります。
その点、両方の許認可を取得しておくことで、遺産整理や生前整理の現場で見つかった酒類を適法に買取・販売できる体制が整い、ワンストップでサービス提供が可能になります。
「不要品の整理」と「価値ある品の再流通」を同時に実現できる点において、遺産整理業との親和性は非常に高いといえるでしょう。
ポイント:古物商許可を取得するなら
古物商許可は簡単に申請できると思いがちなのですが、慣れていないと非常に時間がかかってしまいます。
専門的な知識がないと、申請書類の記載内容を間違えていたり、不足書類があったりすることも。そうなった場合には、再度提出が必要です。
当事務所では、古物商許可も専門で対応しております。
興味がある方は、ぜひ下記からご確認ください。
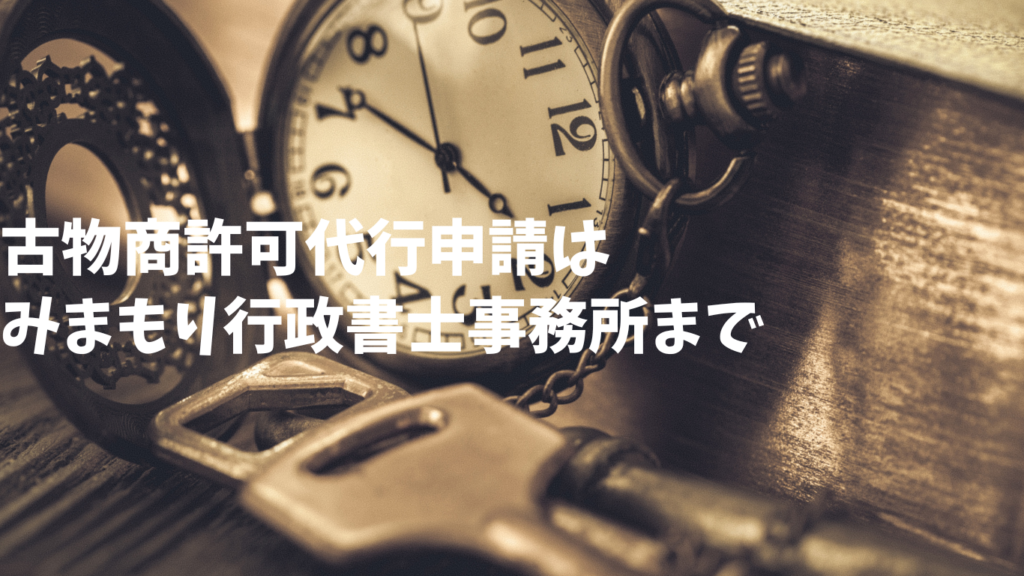
4.まとめ
以上、中古のお酒を販売するのに必要な許可は酒類販売業免許?古物商許可?を解説いたしました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい