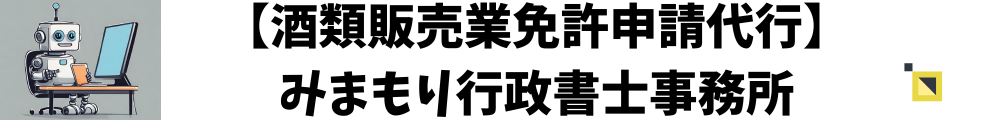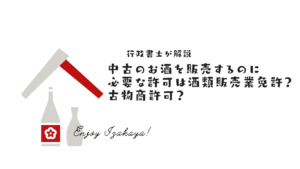【酒類販売業免許】副業でお酒を販売したい!

【酒類販売業免許】副業でお酒を販売したい!
Contents
1.副業でお酒を販売したい!

①副業が当たり前の時代に
近年、副業を認める企業が増えたことや、個人の働き方が多様化したことを背景に、「自宅でできる副業」「ネットを活用した副収入」といったテーマに注目が集まっています。
その中でも、サントリー「山崎」や「白州」、ニッカの「竹鶴」など、国産ウイスキーの品質が国内外で高く評価され、プレミア価格がつくほど需要が急増していることを背景に、お酒を販売したいという方もう増えてきています。
しかし、酒類を販売するためには「酒類販売業免許」が必ず必要であり、無許可での販売は違法行為に該当します。たとえ少量であっても販売行為にあたる以上、免許取得が前提になります。
②お酒の販売には免許が必要です!

ポイント:お酒の販売は酒類販売業免許が必要。
不用品の販売なら免許不要
仕入れたお酒を販売する場合には「酒類販売業免許」が必要です。
ただし、自宅にあるなどの不用品のお酒を販売する場合には酒類販売業免許は必要ありません。
お酒を仕入れて販売するなど継続的に事業を行う場合には、酒税法の規定に基づき、各販売場ごとにその所在地を管轄する所轄税務署長から酒類販売業免許を取得する必要があります。
ポイント:許可要件をクリアする必要がある
酒類販売業は誰でも始められるわけではありません。
酒販免許は国税庁(税務署)が管轄しており、取得するためには酒税法に基づく4つの条件(法律用語では「要件」といいます)を満たす必要があります。
酒類販売業の免許取得要件
- 人的要件
- 税金の滞納処分を受けたことがないこと。
- 各種法令違反や罰則を受けていないこと(もし受けていた場合、一定の期間が経過していること)。
- 場所的要件
- 酒類販売を予定している場所が適切であること。
- 経営基礎要件
- 免許を取得して酒類販売を行う者(法人または個人)の資金、経営状態、経験が、酒類販売にふさわしいものであること。
- 需要調整要件
- 酒類の仕入れや販売を適正な方法で行えること。
- 販売価格や品質を適正に維持できること。
これらの要件をクリアし、酒類を販売する事業者として適切であると認められて初めて、免許の取得と酒類販売が可能となります。
酒類販売業免許の許可要件の詳細に関しては過去の記事で解説しています。
下記からご覧ください。
許可要件の詳細は下記から
ポイント:副業で酒類販売をする場合に注意すべきこととは

では、副業として酒類販売業免許を取得・運営するには、どのような条件を満たす必要があるのでしょうか。次項で解説していきます。
2.副業で酒類販売業免許を取得する場合の注意点

①経営経験が必要
ポイント:経営基礎要件をクリアできるか
酒類販売業免許の取得においては、「販売場を適正に運営する能力があること」が要件となっています。具体的には、次の2つの経験が求められます。
酒類販売業免許で求められる経営経験とは
- 事業の経営経験
- 酒類販売の経験
①−1 事業の経営経験はありますか?
副業・兼業での申請を検討している方の多くは、会社員として勤めつつ酒類販売を行いたいということになります。その場合には、個人名義で酒類販売業免許を取得することになることが、ほとんどでしょう。
しかし、仮に申請者が会社員としての勤務経験しかない場合、原則として経営基礎要件を満たしていないと判断されてしまいます。
ポイント:直近3年分の財務諸表の写しが必要
免許申請時には、「直近3年分の財務諸表の写し」の提出が必要です。
これにより経営経験があるかどうかが審査されます。
法人の登記上の役員でもなく、個人事業主でもなければ、財務諸表の写しを提出することは難しいでしょうから、酒類販売業免許の申請がそもそもできません。
①−2 酒類販売の経験がありますか?
「酒類販売業」とは、酒販店・スーパー・コンビニ・ディスカウントストアなどにおいて、酒類を小売として取り扱う業務を指します。
過去に酒類を扱う小売業でアルバイトなどの形で勤務していた場合は、たとえ短期間であっても、一定の経験として加味される可能性があります。学生時代のアルバイト経験なども、「全くの未経験」という状態よりはプラスに働くこともあります。
また、飲食店での接客業務や、お客様にお酒を提供する業務は、原則として酒類販売業の経験には含まれません。
たとえば、居酒屋やレストランで働いた経験があっても、「販売」ではなく「提供」に当たるため、申請時の実務経験としては評価されにくいという点に注意が必要です。
ただし、酒類を日常的に扱っていた実績があるという点で、多少の考慮がなされることもあります。
ポイント:職歴書で確認される
酒類販売の経験があるかどうかは、職歴書で確認されます。
酒類販売の経験がないからといって、自身の経歴を捏造することはNGです。
そもそも酒類販売の経験がなくとも、別の方法でクリアすることは可能です。
ポイント:業務経験がない場合には酒類販売管理研修を受講
もし業務経験がない場合には、「酒類販売管理研修」の受講などで酒類販売の知識や能力を評価されることもあります。
要するに、酒類販売業免許は「酒類販売管理研修」を受講することによって、経営基礎要件を満たすことができる場合があるということです。
酒類販売管理研修について詳しく知りたい方は過去の記事で解説していますので、下記からご覧ください。
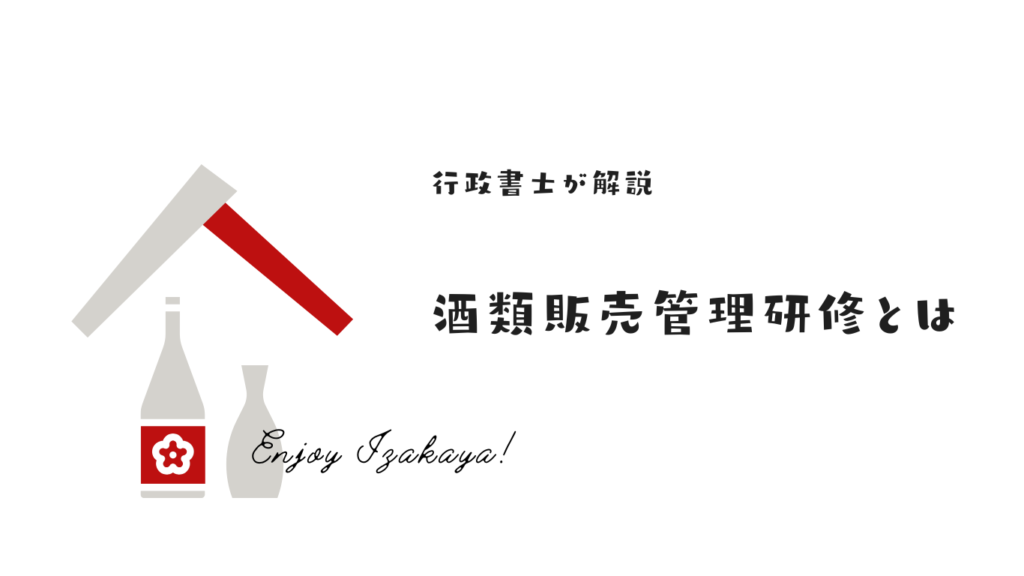
②酒類販売のための場所の確保が必要

ポイント:場所的要件をクリアできるか
免許を取得するには、「販売場」として使用する物件を確保しなければなりません。
副業で自宅を利用するケースも多く見られますが、以下の点に注意が必要です。
酒類販売業免許で求められる場所的要件とは
- 販売場が自己所有か、賃貸であれば使用承諾が得られること
- 物件の用途地域が、酒類の販売に適していること(都市計画法上の制限)
- 賃貸借契約に使用目的が明記されている場合は、店舗利用が可能かどうか
など
例えば、使用しようとする物件が賃貸で「住居専用」や「事務所限定」といった制限がある場合は、酒類販売の用途で使えない可能性があり、貸主の承諾書の提出が必要になることがあります。
③本業以外の時間で酒類販売を継続的に運営できるか

ポイント:需給調整要件をクリアできるか?
副業として申請する場合、販売場を適切に管理・運営できる時間的余裕があるかも問われます。
販売業は継続性が前提であり、免許取得後に「実際には販売していない」「仕入れもしていない」といった実態があると、問題視される可能性があります。
そもそも免許を取得した後には、年度(4月1日から翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量を翌年度の4月30日までに、毎年度報告する必要があります。
酒類の販売数量等報告書
酒類の販売数量等報告書は、年間の酒類販売数量を記載し、4月30日までに所轄税務署に提出する必要があります。以下が記載の要点です。
- 販売数量の記載
- 卸売販売数量(卸売業者、小売業者向け)、小売販売数量(一般消費者や業者向け)をそれぞれ記載。返品分は差し引き、輸出分は含めない。
- 在庫数量の記載
- 3月末時点の在庫数量(輸出用も含む)を記載。
- 業態の記載
- 提出時の販売場の業態に応じた区分にチェックを入れる(例: ワイン専門店は「①」)。
お酒の仕入れや販売の実態がない場合には、酒類販売業免許取得の必要性がないため、免許取消になってしまう可能性も否定できません。
④就業規則で副業・兼業が禁止されていないかを確認
会社に勤めながら副業として酒類販売を行う場合、まずは所属する企業の就業規則や雇用契約書に「副業禁止」などの条項がないかを確認しましょう。
無断で申請を進めると、免許取得後にトラブルになる可能性があるため、状況によっては、副業NGの記載がない就業規則や、副業を承諾する旨の書面の提出が求められる場合があります。
⑤取得する免許によって販売できるお酒の種類や方法が限られる
酒類販売業免許にはいくつかの種類があり、それぞれの免許ごとに「どのような酒類を」「どのような方法で」「どこに向けて」販売できるかが異なります。
そのため、免許の種類によっては、希望していた酒類を販売できなかったり、インターネット販売が制限される場合があります。
特に、現在人気の出ている国産ウイスキーをインターネットで販売することは原則できません。ただし、条件付きで販売できる場合もありますので、詳しくは過去の記事に記載していますので、下記からご確認ください。
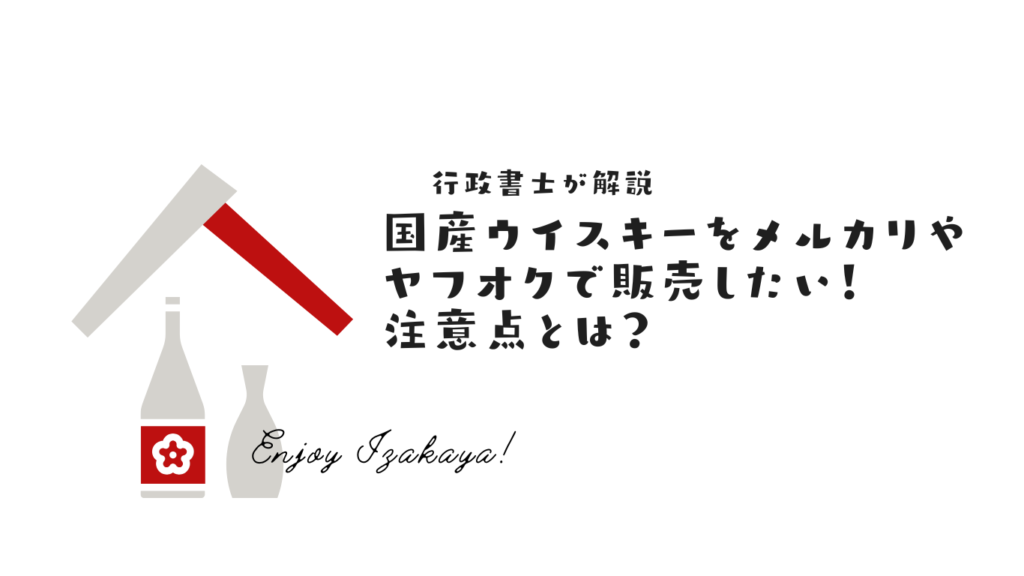
3.まとめ
以上、【酒類販売業免許】副業でお酒を販売したい!を解説いたしました。
専門的な知識がないと

何度も書類を書き直したり
申請先に足を運ぶなど
ただただ時間が取られてしまいます!
お問い合わせは下記から
お気軽にお問い合わせください。092-725-2275受付時間 8:00-20:00 [ 土日祝対応可 ]
お問い合わせ お気軽にお問い合わせ下さい